はじめに:80代ご夫婦のお宅で感じたこと

先日、80代のご夫婦のお宅に、訪問サポートで伺いました。
ご主人は現在入院中とのことで、「しばらく掃除できていない夫の部屋をきれいにしてほしい」と、奥様がお困りの中でご依頼をくださいました。
押入れには、十数年動かしていない布団がぎっしり。衣装ケースにはセーターがたくさん、ハンガーには立派なお洋服が並んでいましたが、全てほこりをかぶっていて、虫食いで穴があいているものもありました。
奥様は、
夫がね、「俺が生きているうちは何も捨てるな」っていうんですよ。
子どもたちからは整理するように言われているけれど、一人ではなかなかできなくて…
と、ため息をつかれていました。
今回のサポートは、ただ部屋をきれいにするだけではなく、「高齢のご夫婦の暮らしの背景に触れた時間」でもありました。
親に「片づけて」と言うだけでは片づかない理由

①体力が落ちると、片づけの作業そのものが難しくなる
押入れの布団を出す、家具を少し動かす。
若い頃なら当たり前にできたことが、年齢を重ねると本当に重労働になります。
「やりたい気持ちはあるのに、身体がついていかない」
そんな状態の方がとても多いです。
②判断にもエネルギーが必要になる
何を残して、何を手放すか。
この「選ぶ」という作業は、想像以上にエネルギーを使います。
迷う時間が長くなったり、決められなくなっていくのは、自然なことなのだと思います。
③長年の思い入れや家族への責任感
今回のご主人が
「俺が死ぬまでは何も捨てるな」
と言われるように、長く生きてきたぶん、大切にしたい物や価値観も積み重なります。それが片づけのハードルを上げてしまうこともあるのです。
遠方に住む子ども世代が直面するもどかしさ

手伝いたいのに、手伝えない現実
お子さんが関西と関東で暮らしているという今回のご夫婦のように、子ども世代と離れて暮らしていると、
「見に行きたいけれど時間がとれない」
「様子を見に行くたびに状態が変わっている」
そんなことが起こります。
親の現状が見えにくい
また、どこまで自分でできて、どこが難しいのか。
一緒に住んでいないと、親の細かな変化には気づきにくいものです。
まずは「観察」と「対話」から
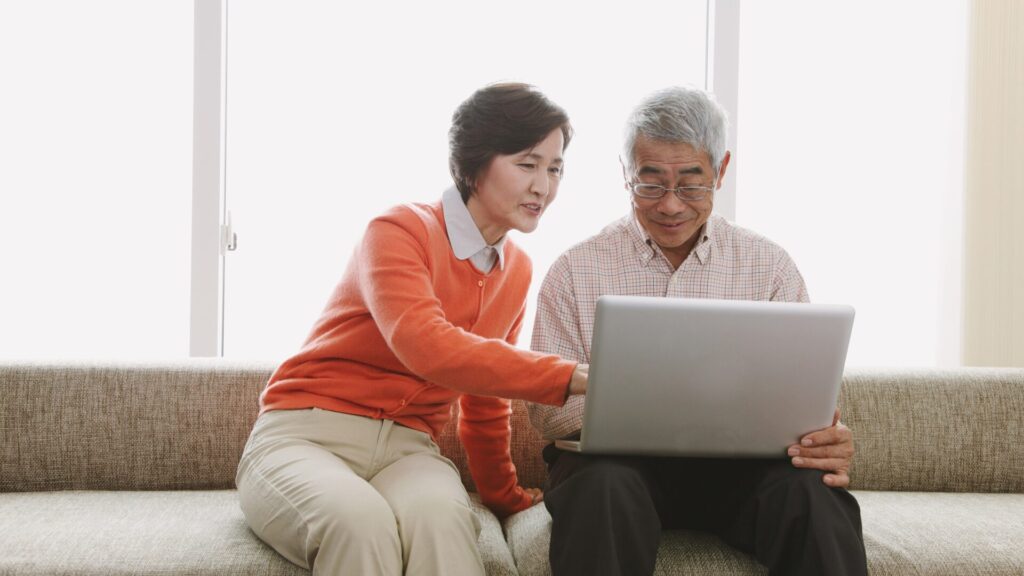
今の親の「できること」を見てみる
・重いものは持てる?
・しゃがむ、立つはスムーズ?
・判断に時間がかかっていない?
こうした小さな観察が、サポートのヒントになります。
押しつけではなく、気持ちを聞く
「これはどうしたい?」
「何が困ってる?」
そんな対話の積み重ねが、片づけの一歩をやさしく後押ししてくれます。
必要であれば、子世代が外部サービスを整えてあげる
高齢の方にとって、「サービスを探す・比較する・申し込む」という一連の流れは、思っているより負担が大きいです。
だからこそ、
・どのサービスが良さそうか調べてあげる
・予約や相談を代わりにしてあげる
・必要な範囲だけ外部に頼む
こうした形で子ども世代がサポートすると、親御さんも安心して任せやすくなります。
遠方に住んでいても、
外部の手をそっと添えることで、親の暮らしはぐんと楽になります。
まとめ:家族だけで抱えなくて大丈夫です
「片づけられなくなってきた親」を目の前にすると、心配や不安を感じるのは自然なことです。
でも、家族だけで全部を抱え込まなくて大丈夫。
必要に応じて、プロの力を借りることは、親御さんにとってもご家族にとっても、やさしい選択だと思います。
【訪問片づけサポートのご案内】
もし、
・実家の片づけが心配
・遠方で思うように手伝えない
・第三者に少し手伝ってほしい
そんな想いがあれば、どうぞ気軽にご相談ください。
ご家族の気持ちを大切にしながら、無理のないペースで進める「訪問片づけサポート」をお届けしています。オンラインでの事前相談も可能です。


